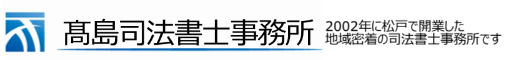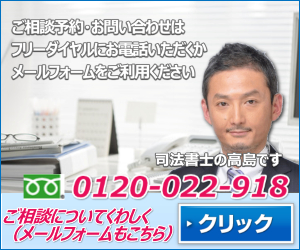(最終更新日:2025年1月31日)
相続登記の手続きを進めていく際に、複数の相続が関係してくることがあります。不動産の所有者が亡くなったことにより相続が開始したものの、その相続登記をしないでいるうちに、さらにその相続人であった方が亡くなってしまったような場合です。このように複数の相続が発生している状態を、数次相続(すうじそうぞく)といっています。
なお、このページで解説しているのは、不動産登記の手続きをおこなう専門家以外には通常必要のない知識についてです。司法書士への相続登記の相談、依頼を検討なさっている方は、当事務所による相続登記(相続による不動産の名義変更)のページをご覧ください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、数多くの相続登記やその他の不動産登記手続きを取り扱ってまいりました。数次相続や代襲相続の関連する難しい相続登記、複雑な相続登記のことでも、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
数次相続による相続登記(目次)
1.数次相続とは
2.数次相続による相続登記の手続き
2-1.数次相続の場合の遺産分割協議書
2-2.相続登記における登記原因
2-3.数次相続による登記で、中間省略登記が認められる場合
2-4.最終の相続人が複数の場合
2-5.最終の相続人に直接登記ができない場合
2-5-1.中間が単独相続でない場合
2-5-2.最終相続人が1人のみの場合
3.相続人が不存在の相続人がいる場合

1.数次相続とは
ある方の死亡により相続が開始したが、遺産分割協議や相続登記を行わないでいるうちに、相続人の1人が亡くなってしまったとします。このように、前の遺産相続の手続きをしないうちに、次の相続が開始してしまっている状態を数次相続といっています。一つ目の相続(第1次相続)に、二つ目の相続(第2次相続)が続いているわけです。

上の図では、平成30年に夫Aが亡くなった際の法定相続人は妻B、長女C、長男Dの3人でした。しかし、遺産分割協議や相続登記などの遺産相続手続きをおこなわないでいるうち、令和5年に長男Dが亡くなってしまいました。
この場合、長男Dに属していた、父であるAに対する相続権を、その法定相続人である長男の妻E、子1F,子2Gが相続することになります。よって、夫Aが所有する不動産についての遺産分割協議に参加すべきは、妻B、長女Cに加え、長男の妻E、および子1F,子2Gであり、その相続分は下図のとおりです。

複数の相続が関連する点で、代襲相続との違いが分かりづらいかもしれません。しかし、被相続人よりも先に子が亡くなっているときなどに代襲相続が生じるのに対し、数次相続の場合には長男D自身がいったんは法定相続人となっています。そして、長男Dが存命のうちに遺産相続手続きをおこなっていたとすれば、何も特別なことはありませんでした。
ところが、夫A(長男から見ると父)の遺産相続手続きをおこなう前に長男Dが死亡してしまったため、その持っていた相続権が、長男Dの法定相続人である長男の妻E、および子1F,子2Gに相続されたわけです。
代襲相続との大きな違いは、子の妻(本例では長男の妻E)にも義父の遺産に対する相続権があることです。これは、妻が、夫(被相続人の長男)を代襲相続して、義父の相続人となったわけではなく、夫が持つ相続権をその相続人として引き継いだからです。
目次に戻る
2.数次相続による相続登記の手続き
上図のようなケースで、妻が不動産を引き継ぐとします。この場合、相続人全員(妻B、長女C、長男の妻E、子1F,子2G)により、遺産分割協議をおこない、その結果を記した遺産分割協議書を作成、添付することで相続登記の申請をおこないます。
2-1.数次相続の場合の遺産分割協議書
数次相続の場合の遺産分割協議書では、誰が被相続人であるのか、また、誰の相続人として協議に参加するのかが分かるように書きます。たとえば、上図のケースでは当事者を次のように記載すればよいでしょう。当事者以外の作成例については、遺産分割協議書のページをご覧ください。また、相続人中に未成年者がいる場合には、未成年者のための特別代理人選任が必要です。
遺産分割協議書(例)
最後の本籍 千葉県松戸市松戸○番地の○
最後の住所 千葉県松戸市松戸○番地の○
被相続人 A(夫) (平成 年 月 日亡)
本籍 千葉県松戸市松戸○番地の○
住所 千葉県松戸市松戸○番地の○
相続人 妻B (昭和 年 月 日生)
本籍 千葉県流山市南流山○丁目○番
住所 千葉県流山市南流山○丁目○番地の1
相続人 長女C (昭和 年 月 日生)
最後の本籍 千葉県柏市柏1丁目○番
最後の住所 千葉県柏市柏1丁目○番○号
相続人兼被相続人 D(長男) (平成 年 月 日亡)
本籍 千葉県柏市柏1丁目○番
住所 千葉県柏市柏1丁目○番○号
上記D相続人 長男の妻E (昭和 年 月 日生)
本籍 千葉県柏市柏1丁目○番
住所 千葉県柏市柏1丁目○番○号
上記D相続人 子1F (平成 年 月 日生)
本籍 千葉県柏市柏1丁目○番
住所 千葉県柏市柏1丁目○番○号
上記D相続人 子2G (平成 年 月 日生)
(以下 省略)
なお、上記のように氏名の前に肩書を入れることにより、誰の相続人としてどのような地位で遺産分割協議書に参加しているのかが明確になりますが、「数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記は、これをすることができる(平成29年3月30日民二237)」との先例もあります。これに従うとすれば、各相続人の肩書きなどは入れなくとも差し支えないことになります。
また、上記先例の中に「上記各相続における相続人又は相続人の地位を承継した者であるFからSまでの全員の署名押印があり、第一次相続から第三次相続までの遺産分割協議をするためにそれぞれ必要な者によって遺産分割が行われたと考えられます」との記述があります。数次相続の各相続における相続人又は相続人の地位を承継した人全員の署名押印があれば良いわけです。
ただし、当事務所で遺産分割協議書を作成する場合には、すべて相続人の肩書きを入れて作成しています。相続人が多数になるときには手間がかかりますが、一人一人に肩書きを入れて慎重に遺産分割協議書を作成することで、相続関係を漏らすような事態を避けられると考えるからです。
目次に戻る
2-2.相続登記における登記原因
上記の遺産分割協議の結果、被相続人の妻Bが不動産を取得することとなった場合、相続登記をする際の登記原因は「平成30年○月○日 相続」です(年月日は被相続人Aの死亡日)。
なお、本例で被相続人の長男の子(被相続人の孫)が不動産を取得することとなった場合でも、一度の登記により、被相続人Aから孫(子1F,子2G)へ所有権移転登記をすることが可能です。この場合、相続登記をする際の登記原因は次のように記載します。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 平成30年○月○日 D相続 ・・・日付は被相続人Aの死亡日
令和5年○月○日 相続 ・・・日付は長男Dの死亡日
(以下 省略)
妻Bが不動産を相続する場合には、被相続人である夫から直接、所有権が移転しています。したがって、登記原因として記載すべきは被相続人Aの死亡日のみです。これに対し、被相続人の孫が相続する場合には、被相続人の子(長男D)がいったん相続(第1次相続)したのを、さらに被相続人の孫が相続(第2次相続)しているわけです。
このような場合であっても、長男Dが単独相続しているときには、被相続人から孫へ1件の申請で相続登記が可能ですが、中間相続の登記原因も併記するのです。
目次に戻る
2-3.数次相続による登記で、中間省略登記が認められる場合
数次相続による相続登記をする際には、それぞれの相続についての登記申請をおこなうのが原則ですが、次に当てはまる場合には中間の相続による登記申請を省略することが認められています。
数次相続による登記で、中間省略登記が認められる場合
- 中間の相続人が1人である場合
- 中間の相続人が数人であったが、遺産分割によりその中の1人が相続した場合
- 中間の相続人が数人であったが、相続の放棄によりその中の1人が相続した場合
- 中間の相続人が数人であったが、その相続人の中の1人以外の相続人が相続分を超える特別受益者であった場合
たとえば、下図の通りの相続関係では、1次相続の相続人は妻B、長女C、長男Dの3人でした。そして、2次相続の相続人は長男の妻E、子1F、子2Gの3人です。そこで、B、C、E、F、Gの5人により遺産分割協議をした結果、Fが不動産を取得することとなった場合、被相続人から直接Fに対する所有権移転登記をすることができます。

本例は、上記の2「中間の相続人が数人であったが、遺産分割によりその中の1人が相続した場合」に当たるからです。もしも、中間省略登記が認められないとすれば、1件目の登記申請で「被相続人から、長男Dに対する所有権移転登記」をした後に、2件目の登記申請で「長男Dから、Fに対する所有権移転登記」することになります。
目次に戻る
2-4.最終の相続人が複数の場合
数次相続による相続登記で、中間の相続による登記申請を省略できるのは、中間が単独相続である場合です。最終の相続が単独であることは条件でないので、最終の相続人が複数の場合であっても、中間の相続による登記申請を省略することができます。
このページで解説している例でいえば、長男の妻および子が共有により相続する場合でも、中間の相続による登記申請が省略できます。つまり、被相続人から、長男の妻および子へ、直接の相続による所有権移転登記がおこなえるわけです。この場合の登記申請書の記載は次のようになります。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 平成30年○月○日 D 相続
・・・日付は被相続人Aの死亡年月日、「相続」の前に長男Dの氏名を書きます。
令和5年○月○日 相続 ・・・日付は長男Dの死亡年月日
相続人(被相続人 A)
住所
持分2分の1 E(長男の妻Eの氏名)
住所
2分の1 F(長男の子1Fの氏名)
(以下 省略)
目次に戻る
2-5.最終の相続人に直接登記ができない場合
2-5-1.中間が単独相続でない場合
第1次相続開始後に、長男と長女が2分の1ずつ相続するとの遺産分割協議をおこなっていたとします。その後、相続登記をする前に第2次相続が開始したため、長男が相続するはずだった2分の1を長男の妻が相続するとの遺産分割協議をしたとします。
この場合、最終的には長女2分の1、長男の妻2分の1の共有名義になりますが、2通の遺産分割協議書を添付しても、被相続人Aから、長女および長男の妻へ1件の申請によって直接の相続登記することはできません。
被相続人Aから、長女および長男への相続登記をした後に、長男からその妻への相続登記をする必要があります。このように、第1次相続が単独相続でない場合には、最終の相続人へ直接、相続登記することは認められていないのです。
2件の申請書の記載は次のようになります(説明に必要な箇所のみ抜粋)。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 平成30年○月○日 ・・・日付は被相続人Aの死亡日
相続人(被相続人 A)
住所
持分2分の1 氏名(長女C)
住所
2分の1 氏名(亡長男D)
(以下 省略)
登記申請書
登記の目的 D持分全部移転
原因 令和5年○月○日 ・・・日付は長男Dの死亡日
相続人(被相続人 長男D)
住所
氏名(長男の妻E)
(以下 省略)
2-5-2.最終相続人が1人のみの場合
相続開始時には、被相続人の妻及び子の2人が相続人だったが、相続登記をおこなわないでいるうちに妻が死亡した場合、妻の生前に遺産分割協議をおこなっていたというような事情が存在しないときには、被相続人から子への直接の相続による所有権移転登記をすることは認められません。
最終相続人が複数の場合には、中間相続が単独であれば、最終相続人に対して直接の所有権移転登記ができるのに対し、最終相続人が1人のときは中間省略登記が認められないわけです。かつては、最終相続人1人による遺産分割協議書(遺産分割決定書)などの書面を添付することで、最終相続人に対して直接の所有権移転登記が可能だったのが、現在では否定されています。
甲の死亡により、配偶者乙と甲乙の子丙が共同相続人となったが、相続登記未了の間に乙が死亡した場合において、甲から丙に相続を原因とする所有権の移転の登記をするためには、丙を相続人とする遺産分割協議書又は乙の特別受益証明書等を添付する必要があり、これらの添付がない場合には、乙丙へ相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で、乙の持分について丙へ相続を原因とする所有権の移転の登記をすべきである。(登研758)
目次に戻る
3.相続人が不存在の相続人がいる場合
数次相続により相続人が多数になっている場合に、その相続人であった人の1人が死亡し相続人が不存在になっているとき、遺産分割協議を成立させ相続登記をするにはどのような手続きが必要になるでしょうか。
相続財産清算人の申立てをおこない、最終的に特別縁故者の不存在が確定することで、民法255条の規定により相続財産法人の持分を他の共有者に帰属させることがまず考えられます。
しかし、当事務所で取り扱ったケースでは、「相続財産清算人によって、相続財産法人の相続分全部を他の相続人に無償譲渡する」ことにより手続きを進めたことがあります。
これにより、存命の相続人のみにより遺産分割協議を成立させ、相続登記をすることが可能となったわけです。
一般的な手続きとは異なるかもしれませんが1つの例としてご紹介します。くわしくは、「相続財産清算人による相続分譲渡からの相続登記」のページをご覧ください。
「相続登記のよくある質問」に戻る
・お問い合わせ・ご相談予約について
相続登記や、その他の不動産登記のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。
登記費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のことなど、どんなことでも結構です。不動産登記についてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は、事務所にお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談である場合を原則とします)。
松戸の高島司法書士事務所ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。
お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら
TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)
電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)
上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時頃まででしたらつながることが多いです。
お問い合わせフォームはこちら