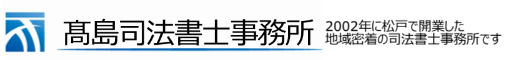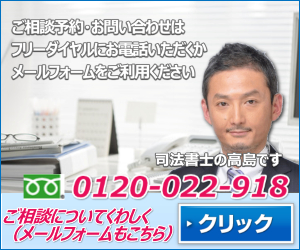(最終更新日:2025年1月28日)
相続財産清算人の選任が必要となるのは、亡くなった人(被相続人)に相続人が存在しないと思われるが、相続財産は存在するときです。また、相続財産管理人選任の申立てができるのは、利害関係人または検察官に限られます。
この利害関係人にあたるのは、相続債権者(被相続人に対する債権者)が債権を回収しようとする場合、遺言により遺贈を受けた特定受遺者が財産を取得しようとする場合、被相続人の特別縁故者に当たると考える人が相続財産を取得しようとする場合などです。
なお、2023年4月1日施行の改正民法により、それまでの「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと名称が変更されています。
相続財産精算人の選任(相続人の不存在)
1.相続財産精算人の選任がおこなわれる場合
2.相続財産精算人選任の申立て
3.特別縁故者への財産分与
4.相続人の不存在と、共有者への持分の帰属
1.相続財産精算人の選任がおこなわれる場合
相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をしたことで、結果として相続する人がいなくなった場合も含む)には、利害関係人などの申立てによって、家庭裁判所が相続財産の精算人を選任します。
相続財産精算人の役割は、被相続人(亡くなった方)の債務の支払いをするなどして清算をおこない、残余財産(清算後に残った財産)を国庫に帰属させることです。また、特別縁故者(被相続人と特別な縁故のあった人)に対する相続財産の分与がなされる場合もあります。
なお、民法による規定では「相続人のあることが明らかでない場合には、家庭裁判所は、利害関係人(または検察官)の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない(民法951条、952条)」と定められています。
法律上の相続人が存在するかどうかは、被相続人についての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などを取得することで明らかになります(ただし、推定相続人廃除については、審判が確定していれば戸籍に記載されますが、相続放棄している場合、相続欠格の場合には戸籍からは判明しません)。
したがって、相続財産清算人の選任が必要となるのは、相続人の存否が不明であるときというより、法律上の相続人が不存在のときと考えて差し支えないでしょう。
また、相続財産清算人の選任が必要なのは、相続財産が存在する場合に限られます。相続財産が何もないのであれば相続財産法人が成立しないので、相続財産清算人選任の要件を満たさないからです。
つまり、財産管理の必要性があるときに、必要とする人(利害関係人など)が選任申立をするわけです。なお、相続財産が極めて少ない場合や、消極財産のみしか存在しないときであっても、法律上は相続財産法人が成立しますから相続財産清算人選任の申立ては可能ですが、手続費用の負担を考えると現実的ではありません。
相続財産管理人選任審判書(例)
2.相続財産清算人選任の申立て
(1) 申立権者(申立てできる人)
(利害関係人にあたる人の主な例)
1.特別縁故者
自らが特別縁故者であるとして財産分与を求めようとする人
2.相続債権者・相続債務者
債権回収をしようとする相続債権者(被相続人に対する債権者)は利害関係人です。また、債務の履行をしようとする相続債務者も利害関係人にあたります。
3.特定受遺者
遺言により遺贈を受けた特定受遺者には、遺贈の目的物である財産の引き渡しや、所有権移転登記の請求権がありますから、利害関係人にあたります。
4.相続財産の共有者
死亡した共有者に相続人が存在しないときは、その持分は他の共有者に帰属します(民法255条)。ただし、この規定が適用されるのは、相続債権者や受遺者がおらず、特別縁故者への財産分与もおこなわれなかった場合(または、財産分与等をおこなっても、不動産の共有持ち分が相続財産の中に残っていた場合)に限られますから、まずは相続財産管理人の選任が必要であり、相続財産の共有者は利害関係人にあたります。
(2) 申立てをする裁判所
- 相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所
(3) 必要書類等
相続財産清算人選任の申立てには次のような書類が必要です。相続財産清算人が選任されるには、戸籍上相続人がいないことを明らかにしなければならないので、多くの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などが必要となります。
- 相続財産清算人選任審判申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(およびその代襲者)で亡くなっている方がいる場合、被相続人の子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合、兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の兄弟姉妹の代襲者(おい、めい)で亡くなっている方がいる場合、おいめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 相続財産についての資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、銀行預金通帳写し,残高証明書など)
- 申立人の利害関係を証する資料
- (相続財産清算人の候補者がいる場合)候補者の住民票
(4) 申立てに必要な費用
- 収入印紙 800円
- 郵便切手 1010円分(東京家庭裁判所の場合)
上記のほかに、官報公告料等の予納金の納付が必要になります。被相続人の流動資産(預貯金・現金)が十分にない場合、予納金の額は原則として100万円となるようです(東京家庭裁判所の場合)。
3.特別縁故者への財産分与
相続人の不存在が確定したときには、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができるとされています(民法958条の3第1項)。
被相続人と生計を同じくしていた者として、特別縁故者にあたるとされるのは、親族または親族と同視し得る人だといえます。たとえば、内縁配偶者、事実上の養子、子の配偶者、叔父、伯母(叔母)、継親子(継母)が特別縁故者だとして財産分与を受けた例があります。
上記の「被相続人と生計を同じくしていた者」は、「被相続人の療養看護に努めた者」にもあたることが多いので、この類型で特別縁故者に該当するとされるのは、被相続人と生計を同じくしていなかった親族や、親族ではない知人であることになります。
4.相続人の不存在と、共有者への持分の帰属
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属するとされています(民法255条)
不動産を2人で共有していたとして、その内の1人が死亡して法定相続人がいないときには、もう1人の共有者にその持分の所有権が帰属するわけです。
ただし、共有者が死亡し、戸籍上の法定相続人が存在しなかったとしても、ただちに民法255条の規定が適用されるわけではありません。戸籍上の法定相続人がいないときでも、相続債権者や受遺者に対する弁済、特別縁故者に対する財産分与をおこなう必要があるのです。
そして、相続債権者や受遺者がおらず、特別縁故者への財産分与もおこなわれなかった場合(または、財産分与等をおこなっても、不動産の共有持ち分が相続財産の中に残っていた場合)にはじめて、民法255条の規定が適用になります。
(もっと詳しく)相続人の不存在と、共有者への持分の帰属
相続手続きのご相談へ
お問い合わせ・ご相談予約について
相続登記その他の不動産登記や遺産相続手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。相続登記や、その他の遺産相続手続きのご相談はいつでも無料でうけたまわっております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。
松戸の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。
お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら
TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)
電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)
上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時頃まででしたらつながることが多いです。
お問い合わせフォームはこちら
※相続登記その他の不動産登記や相続手続きのことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。